「iDeCoって実際どうなの?」「NISAとiDeCoってどっちがいいの?」
そんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。
私は、NISAをメインにしつつ、iDeCoも毎月5,000円だけゆるっと続けています。
でも正直なところ、iDeCoを今から始める方には「慎重に考えてから決めたほうがいいかも」と思うことも…。
今回は、iDeCoも使っているけれど全面的に推しているわけではないという立場から、
リアルなメリット・デメリットを、NISAとの違いとあわせてお話ししていきます😊
わたしのiDeCoとの付き合い方
もともとは、iDeCoの「掛金が全額所得控除になる」というメリットに惹かれて、4年ほど前に開始。12,000円/月・年間144,000円から始めました。
始めたころは旧NISAでつみたてNISAを満額(33,333円/月・年間40万円)利用しており、
「iDeCoもやっておいたほうがいいかな」という軽い気持ちでした。
ですが、2024年に新NISAが始まってからは、資金の優先度がNISAにシフト。
今は、月5,000円だけの少額でiDeCoを継続しています。
なぜ5,000円だけ続けているかというと……
60歳になった頃に「iDeCoやってたこと忘れてた!」となりそうだからです!!😂😂😂
iDeCoでの所得控除は“おまけ”感覚で、完全に老後用。
60歳まではコツコツ積み立てていくつもりです。
※投資商品は、はじめから一貫して「全世界株(現在は、楽天オルカン)」だけです。
iDeCoのメリット
iDeCoには、他の制度にはない魅力もあります。
- ✅ 掛金が全額所得控除になる(節税になる)
- ✅ 運用益も非課税
- ✅ 原則60歳まで引き出せないため、老後資金の確保にぴったり
- ✅ インデックス型の低コスト商品も選べる
特に、積み立てている間も節税効果があるから節税メリットがNISAよりすぐに実感できます😊
それでも「慎重に」と思う理由
実際にiDeCoを使ってみて、「これは注意が必要かも」と感じた点もあります。
- ⚠️ 原則60歳まで引き出せない
→ 教育費や住宅費に使いたくなってもNG。 - ⚠️ 口座管理手数料がかかる
→ 毎月200円ほど必要。初回のみの加入手数料(2,829円)も発生します。 - ⚠️ 控除の恩恵は人によって異なる
→ 専業主婦(夫)や扶養内の方は、所得控除の効果が小さいです。 - ⚠️ 制度改正リスクがゼロではない
→ 受け取り時の課税ルールが将来変わる可能性も。 - ⚠️ 受け取り方法が複雑
→ 一時金/年金/併用の3パターンがあり、退職金と重なると税金計算が必要に。
つまりiDeCoは、
「掛けているときは節税できるけど、受け取るときに課税されるかもよー」
というちょっとクセのある制度なんです。
NISAとの違いと、私の選び方
NISAは、
- いつでも引き出せる
- 非課税期間が無期限
- 投資上限も大きい
と、iDeCoよりも圧倒的に自由度が高い制度です。
そのため、私は次のように使い分けています👇
- NISA → 将来使う予定のお金(子どもの学費、老後資金など)
- iDeCo → 老後まで使わないと決めたお金(完全に寝かせる。増えてたらラッキー♪)
「せっかく節税になるから!」と、iDeCoを満額使うよりも、
柔軟性の高いNISAに積み立てるほうが、メリットが大きいと感じています。
まとめ:やらないんじゃなく、“自分に合う形で”使うのが大事
iDeCoは、人によって向き・不向きが分かれる制度だと思います。
- ✅ 節税メリットをしっかり受けたい人には向いている
- ❌ お金の自由度を重視したい人には不向き
私の場合は、
- NISAをメインに、iDeCoはサブで少額だけ
というスタイルが、いちばんちょうどいいバランスです。
「やらない」ではなく、
「目的と金額を明確にしておくこと」が、長く続けるコツかもしれません😊
おわりに
「iDeCoやったほうがいいのかな?」「周りがやってるから…」と、iDeCoを始めようか迷っている方がいたら、
“まずはNISAを優先!!”
それでも余裕資金があるり、現役で仕事をしているうちに所得控除を受けたい!などがあれば検討してみてもいいかなぁと思います🍀
わたし自身も、家計や働き方が変わったら、そのときにまた見直すつもりです😊

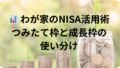
コメント